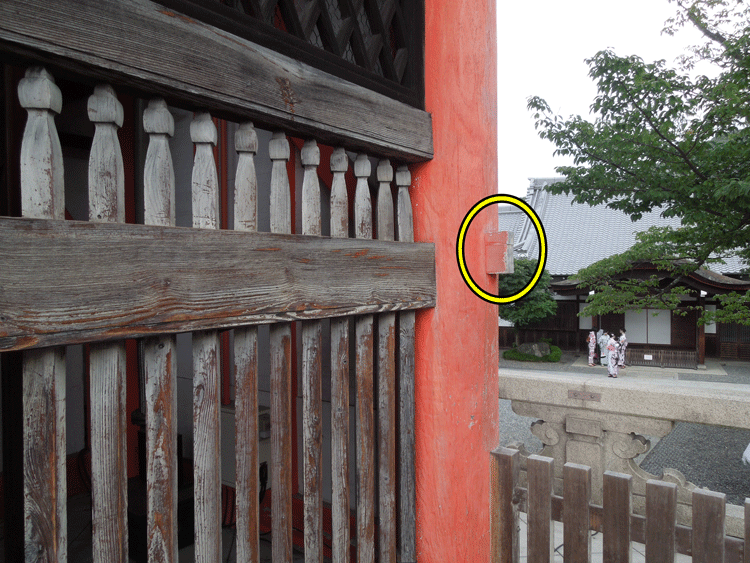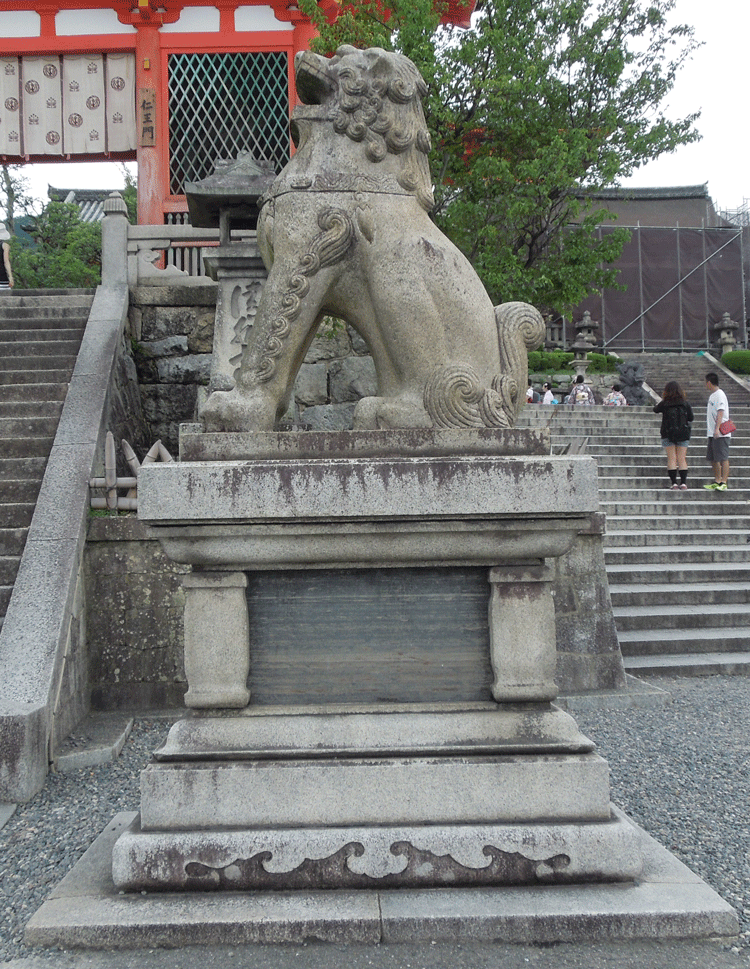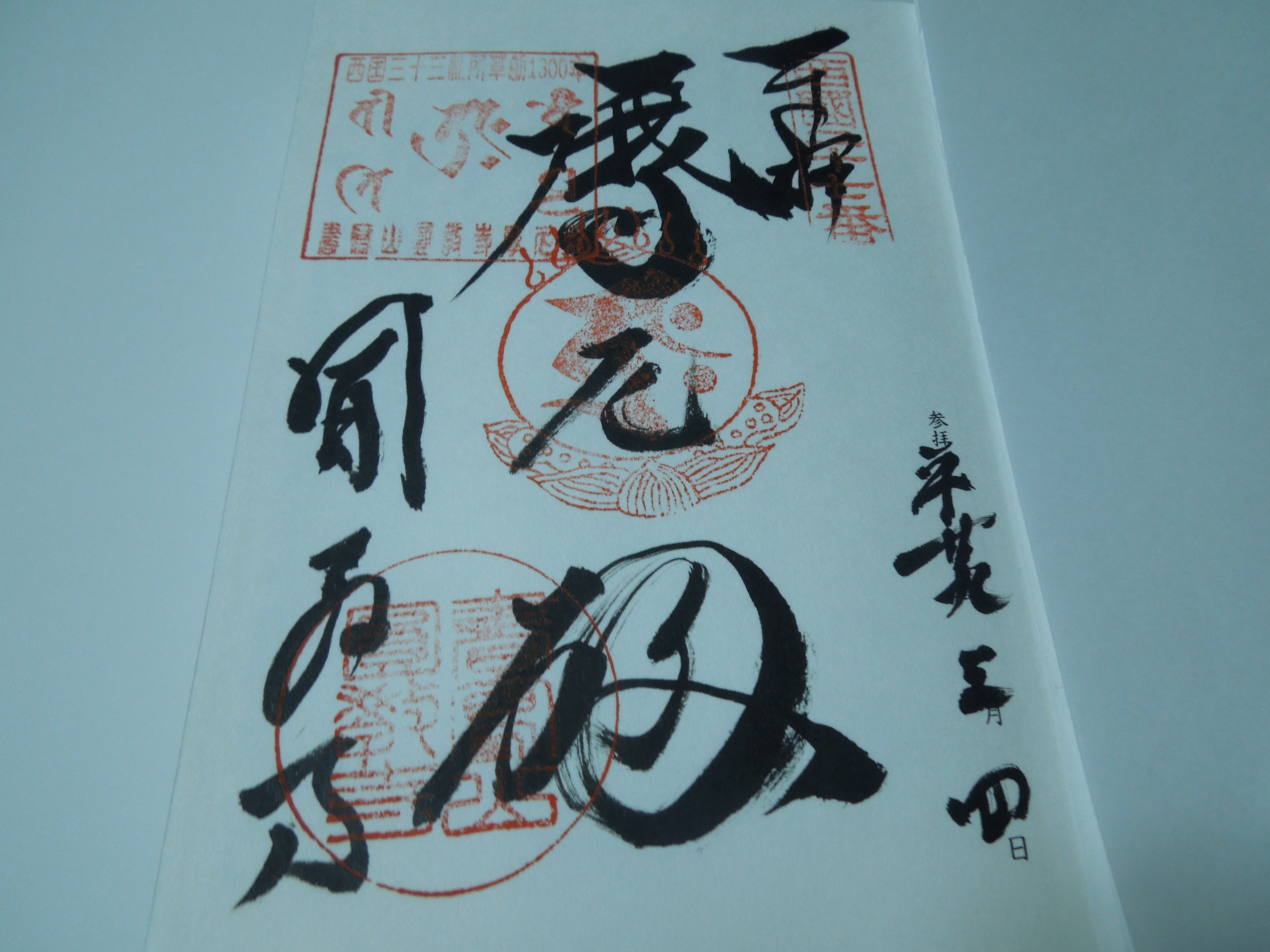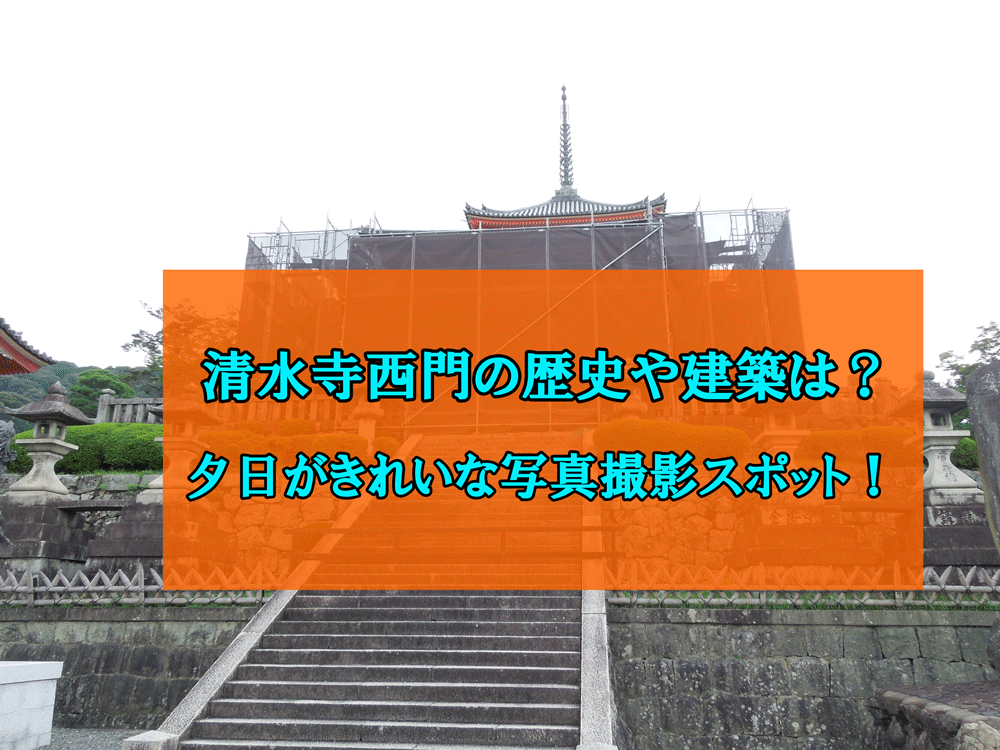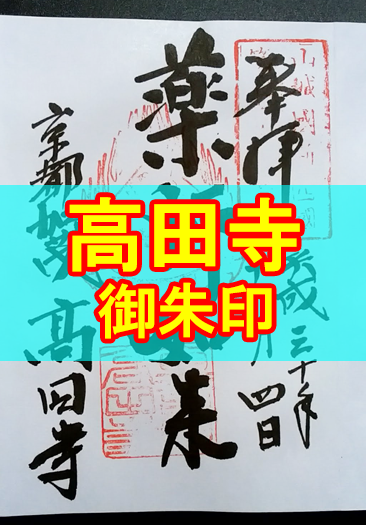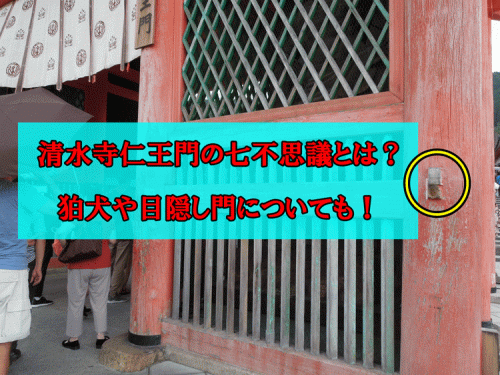
京都の清水寺には七不思議がありますが、清水寺の正門にあたる仁王門にも七不思議に数えられる伝承があります。
さらに仁王門前にある狛犬も通常とは少し異なった形をしています。
この記事では、清水寺仁王門と狛犬について紹介します。
清水寺七不思議のひとつ!仁王門のカンカン貫とは?

清水寺仁王門には腰貫(こしぬき)と呼ばれる部材があります。
腰貫は上の画像の黄色の丸で示した場所にあります。
横から見たのが次の画像。
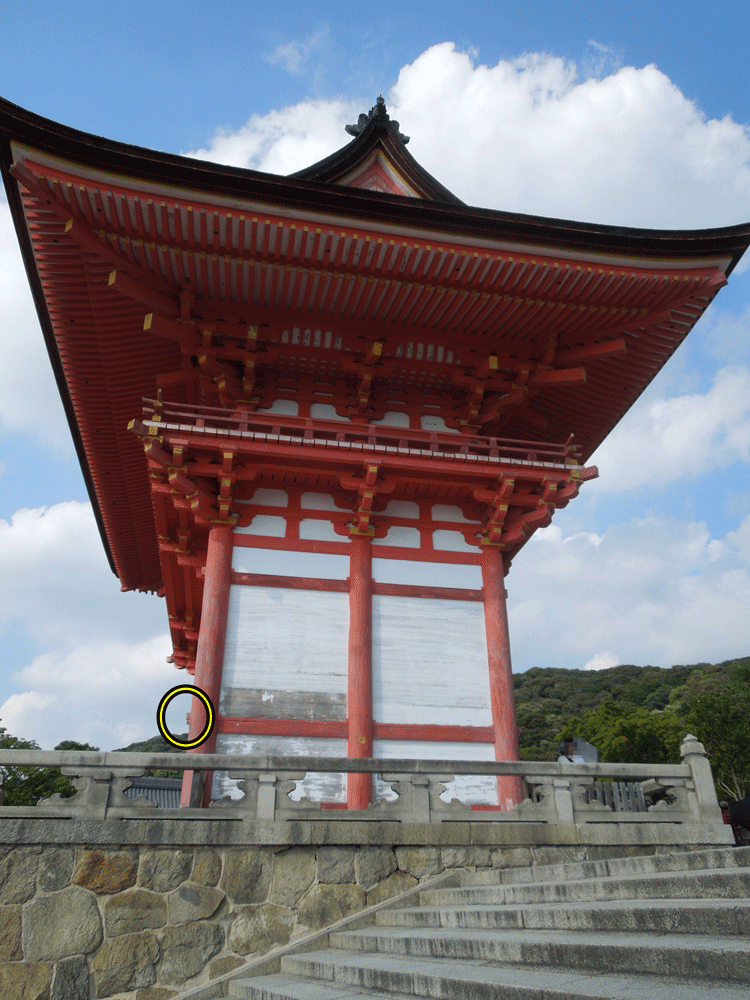
貫(ぬき)とは、木造建築で複数の柱などを固定するために、水平方向に通す木材のことで、
腰貫は、建造物の中央より少し低い位置に通す貫です。
清水寺仁王門の向かって右外側(南西側)の柱の腰貫の頭(出っ張った部分)は大きく凹んでいます。
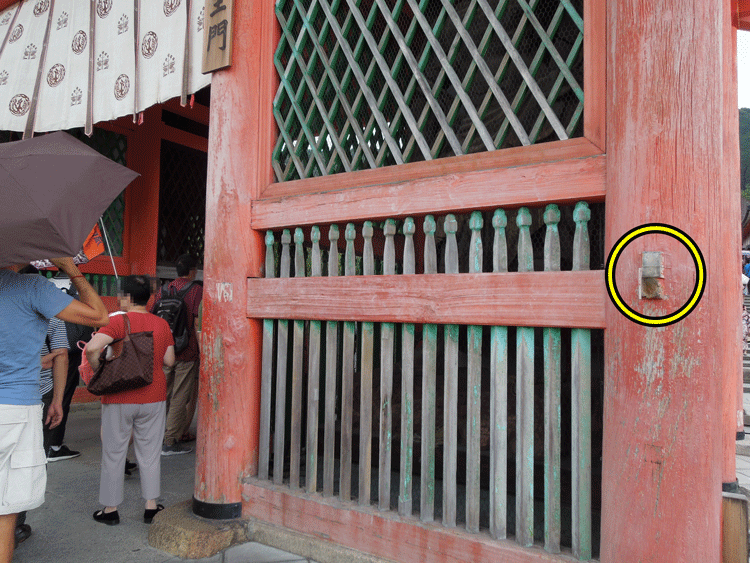
ちょうど上の画像で丸を付けたのが南西側の腰貫です。
凹み具合を確認してみましょう。

画像では少しわかりづらいですが、えぐるように深く凹んでいます。

横から見ても凹んでいることがよくわかります。
この仁王門の凹んだ腰貫は、清水寺の七不思議のひとつとされています。
仁王門の腰貫を叩くと、対角にある腰貫に音が伝わり「カンカン」と聞こえるそうです。
そのため仁王門の腰貫は「カンカン貫」とも呼ばれます。
現存する清水寺の仁王門は、応仁の乱で焼失した後の再建です。
あの腰貫の窪みは、この約500年の間に、多くの人によって叩かれてできたものなのです。
そもそも腰貫を叩いて、反対側から音を聞こうとはじめに誰が考えたのでしょうか。
大工さん?
ある意味、そっちの方が七不思議だと思います。
ちなみに仁王門前面の反対側(北西側)の腰貫の凹み具合は…

全然凹んでいません!
背面に回って見ましょう。

凹みのひどかった南西の腰貫の裏側(南東側)の腰貫です。

こちらもえぐるように凹んでいます。
反対側(北東側)の腰貫も確認します。
凹んでいなかった北西側の腰貫の裏側の腰貫も全然凹んでいません。
4か所の腰貫の凹み具合をまとめると、南側の腰貫が凹んでいるのに対し、北側の腰貫は全然凹んでないということがわかりました。
清水寺仁王門は、重要文化財に指定されている建造物なので、「ぜひ叩いてみてください!」と大きな声でおすすめすることはしません!
もし試すなら当たり前ですけど、二人以上いないと音を確かめられないので、その点はご注意ください(笑)
仁王門前の狛犬は阿吽じゃない?
清水寺の仁王門の前には、一対の狛犬が置かれています。
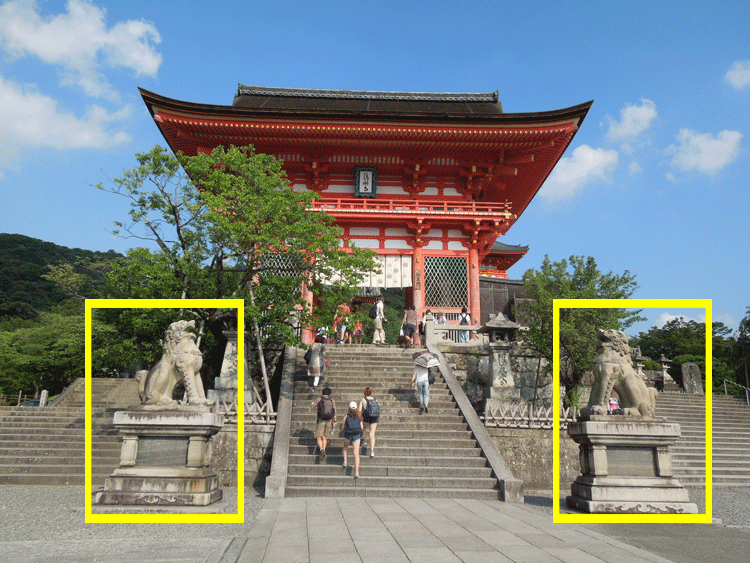
通常、狛犬は片方が口を開いた阿形で、もう一方が口を閉じた吽形ですが、
清水寺仁王門前の狛犬は2体とも口を開いた阿形像です。
現在の狛犬は石造ですが、もともとは金属製の阿吽の狛犬が置かれていました。
1942年(昭和17年)に戦争軍需用の金属供出の際に、金属製の狛犬は徴発されてしまいました。
狛犬がないことを悲しんだ信者団体が1944年(昭和19年)に寄進したのが、現在の石造の狛犬です。
この狛犬は、奈良の東大寺南大門に安置されている石造の狛犬をモデルにしています。

南大門の背面側に一対の狛犬が置かれています。
東大寺仁王門の一対の狛犬は2体とも口を開いた阿形であるため、これを模倣した清水寺仁王門前の狛犬も2体とも阿形像のようです。
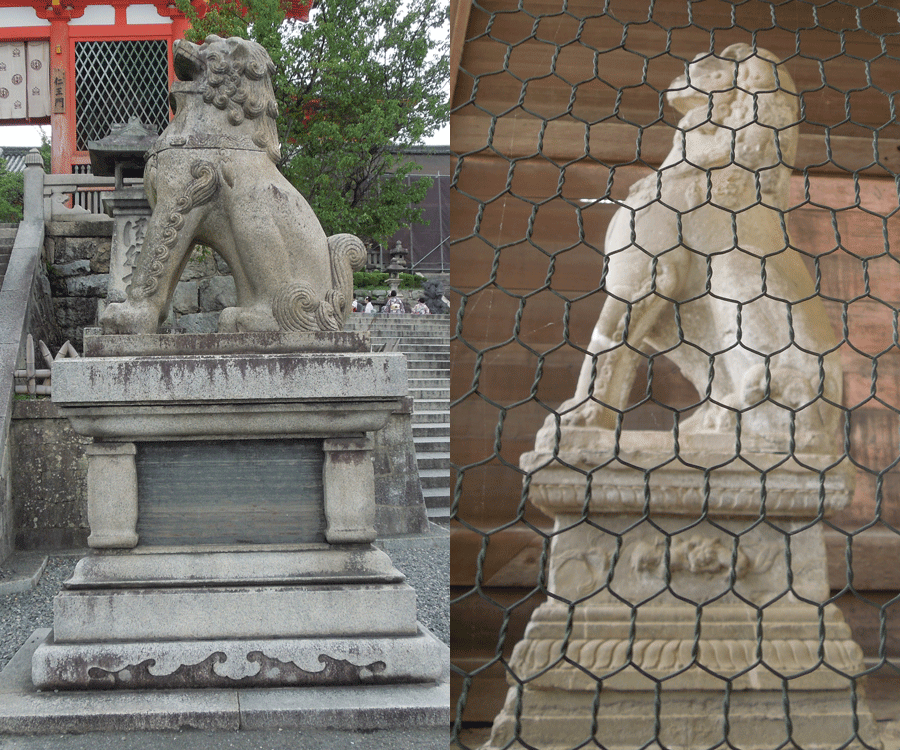
東大寺仁王門の狛犬は金網越しで少し見づらいですが、確かに少し似ていますね。
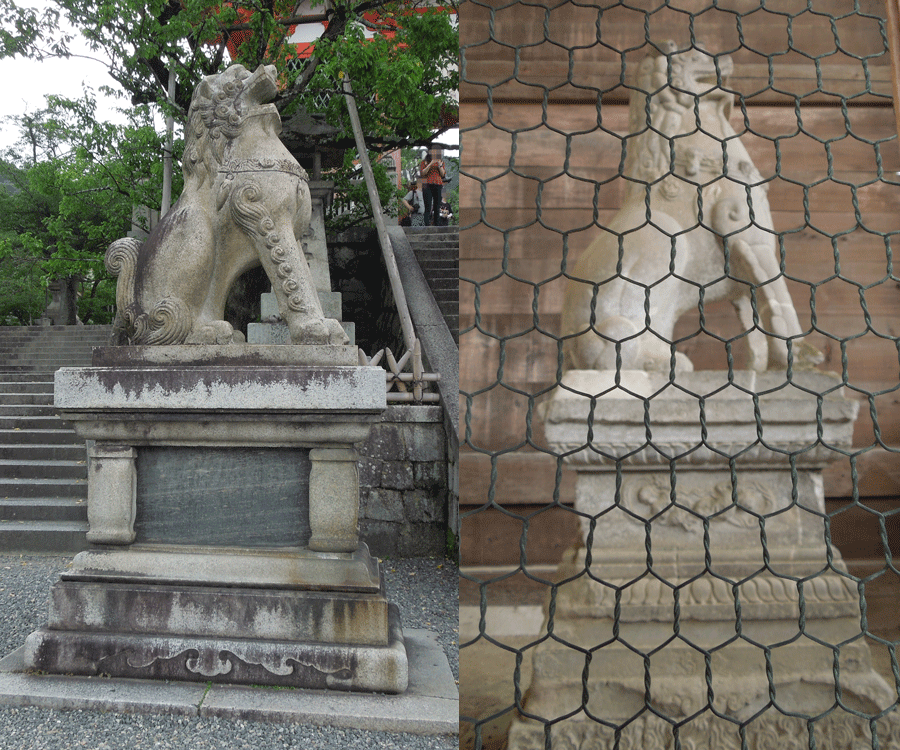
仁王門が目隠し門と呼ばれる理由は?
清水寺の仁王門に「目隠し門」という別名があります。
ある場所を見えなくする(目隠しする)ため、この呼び名があります。
仁王門は西側に向いて建っています。
仁王門の側(南東側)には西門(さいもん)があり、西門も西方に面して建っています。
清水寺の境内は音羽山(清水山)の中腹にあり、西門から京都の市街地を見下ろすことができます。
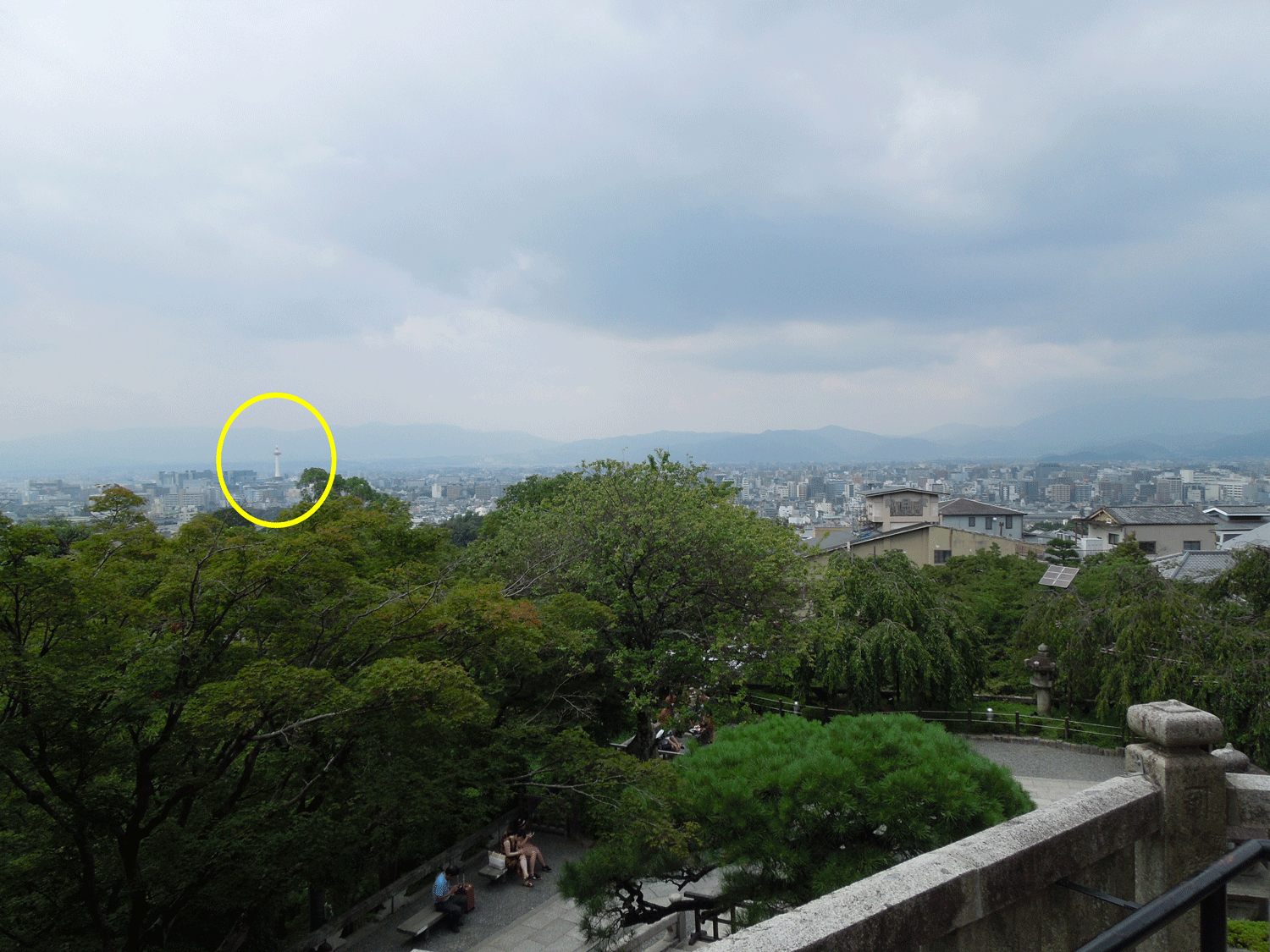
眺めが良くて、京都タワーも見えます。

洛中には平安時代初期から明治時代初頭まで、歴代天皇が居住し、儀式や公務を執り行った京都御所があります。

天皇の御所を直接見下ろすことができないように、仁王門が建てられたとされています。
西門から見て北西の方角に京都御所があり、ちょうどその方角の視界を遮るように仁王門が建っています。

(上の画像撮影時は西門が工事中で、全面に覆いがかけられていたため西門の隣から撮影しています。)
平安遷都の時の御所の場所は、現在の京都御所がある場所より、1.7㎞ほど西にありましたが、
清水寺から見て、京都御所が北西の方角にあることには変わりありません。
(京都御所が現在の位置になったのは14世紀からです。
場所が変わったのは、もともとあった御所が焼失したためです。)
まとめ
- 清水寺の仁王門の腰貫を叩くと、反対側から「カンカン」と音が聞こえる
- 仁王門前の狛犬は2体とも阿形像だが、東大寺南大門像を模倣したもの
- 仁王門は西門から御所が見えないように、目隠し門としても機能している